腎細胞(じんさいぼう)がん
目次
腎細胞がん
腎細胞がんは、腎臓実質の細胞ががん化して悪性腫瘍になったものです。
症状
腎細胞がんは初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため、小さいうちに発見される腎細胞がんは、人間ドック・健康診断や他の病気の検査などで偶然に発見されるもの(偶発癌)がほとんどです。肺や骨、肝臓、脳に転移した症状が出現して、原因を調べる詳しく検査で、腎細胞がんが見つかることも少なくありません。
診断方法
超音波(エコー)検査
がんのある場所や、がんの形・大きさ、がんの周辺の臓器との関係などを確認するために行う検査です。超音波を体の表面にあて、臓器から返ってくる反射の様子を画像にします。
CT検査
一般的には、造影剤を使ったCT検査を行います。造影剤を静脈から急速に注入し、短時間に画像を撮影することで、がんがあると考えられる部位の血液の流れを観察する検査です。また、肺、リンパ節や他の臓器への転移がないかを調べる目的で、胸部のCT検査も行います。
MRI検査
がんの大きさや周囲臓器への広がり(浸潤)、がんかどうかを診断する検査です。強力な磁石と電波を利用して調べます。腎機能障害や造影剤アレルギーなどの理由で、CT検査で造影剤が使えない場合や、CT検査や超音波検査では診断が難しい場合に行います。
腎腫瘍生検
小さい腫瘍でがんであるかはっきりしない場合、画像診断で良悪性の診断がつかない場合、また転移があって腎摘の適応のない進行がんで組織診断をしたい場合に行う検査です。細い針を刺して組織の一部をとり、顕微鏡の病理検査でがんの診断を行います。
骨シンチグラフィ
骨の痛みなどの症状や血液検査の結果などから、骨への転移の可能性が高いと考えられる場合に行うことを検討します。
PET検査
がんの再発や、他の部位への転移を診断するために、他の画像検査をしてもはっきりと診断できない時の補助的な検査として行われることがあります。
血液検査
進行がんや悪性度の高いがんでは、CRPなど炎症反応やLDHやカルシウム値が高値を示す場合や貧血の進行を示す場合があります。
ステージ(病期)
画像診断によりTNM分類(表1)と病期診断(表2)を行い、治療方針が決定します。
表1 TNM分類
| T分類 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| 広がり 大きさ |

|

|
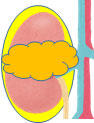
|

|
|
腫瘍が腎臓内 |
腫瘍が腎臓内 |
腫瘍が腎臓を超える |
腫瘍が腎筋膜を超えて周囲に浸潤(副腎、腸管、筋肉) |
|
|
T1a:4cm以内 |
T2a:7~10㎝ |
T3a:周囲脂肪、腎盂、腎静脈に浸潤 |
||
| N分類 | N0 | N1 | ||
| リンパ節転移なし | リンパ節転移あり | |||
| M分類 | M0 | M1 | ||
| 遠隔転移なし | 遠隔転移あり |
表2 病期分類
| ステージ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
| 大きさ | 7㎝以下 | 7㎝以上 | 関係なし | 関係なし |
| 広がり | 腎臓内に留まる | 腎臓内に留まる | 腎周囲脂肪浸潤 | 腎筋膜外浸潤 |
| 所属リンパ節 | なし | なし | あり | 関係なし |
| 遠隔転移 | なし | なし | なし | あり |
| まとめ | T1かつリンパ節 や遠隔転移なし |
T2かつリンパ節 や遠隔転移なし |
T3または リンパ節転移あり |
T4または 遠隔転移あり |
治療方法
転移のない腎細胞がん
小径腎がん(T1)
ロボット支援腎部分切除を行い、可能な限り腎機能を温存します。がんが存在する腎臓を部分的に切除します。残った腎臓の機能を温存でき、長期的な成績では、腎機能の低下とそれに伴う合併症への影響を小さくなるため、標準的な術式となっています。
大きい腎がんや腎臓深部で温存手術が困難な場合
腹腔鏡下またはロボット支援腎摘術を行います。がんのある側の腎臓をすべて取り除く術式です。腫瘍や患者さんの状態から、腎部分切除術の実施が適切ではない場合に選択されます。通常は、手術で片方の腎臓を摘出しても、残った片方の腎臓で機能を補うことができるため、日常生活に支障を来すことはあまりありません。
リンパ節転移や周囲への浸潤や下大静脈までがんが進展する場合
開腹による根治的腎摘除術 を行います。根治切除困難が予想される場合は、術前に分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬による薬物療法を行い、効果があった場合に摘出手術を検討します。
小径腎癌で腎機能や全身状態が不良な場合
- 凍結療法:腫瘍に対して体の表面からニードル(針)を刺し、直接的アルゴンガスを用いて腫瘍を凍結させ、死滅させる方法です。一般的には4㎝以下の腎細胞がんが適応となりますが、腫瘍の大きさや部位によって穿刺が困難な場合もあり、治療の適応は厳密に判断します。一般的には、腎細胞がんが多発する疾患(von Hipple Lindau病)、既に片側の腎臓を何らかの理由で摘出している方、腎機能が低下して腎機能を温存したい方、合併疾患や全身状態により全身麻酔に耐えられない方などがよい適応です。凍結治療は手術と比較すると、局所再発率が高くなりますが、入院期間が短く、体への侵襲が少ない点がメリットです。
*凍結療法は、横浜市大病院へ紹介します - 監視療法:手術などの治療をせず、画像検査を定期的に行い、経過観察する方法です。腫瘍が小さく、腎臓内にとどまる早期がんで、超高齢者や全身状態が不良で治療のリスクが高い患者さんでは選択肢の1つとなります。
転移を有する腎細胞がん、再発腎細胞がん
他の臓器への転移がある、もしくは手術が難しい進行腎がんには薬物療法を用います。薬物療法には、分子標的治療、免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬)があります。この両薬剤の開発によって、進行腎細胞がんの治療成績は格段に向上しました。
分子標的薬(TKI・mTOR阻害薬)や免疫チェックポイント阻害薬(ICI)による薬物治療を行います。IMDCリスク分類(表2)により、投与薬剤が決まります。治療効果を向上させるために、上記薬剤を2剤併用する強力な治療法を行うことが多くなりました。また、先行の薬剤が無効になった場合は、漸次薬剤を変更します。
転移を有する腎細胞がん(淡明細胞癌)のIMDCリスク分類別の一次治療について説明すると、低リスク群では、TKI+ICIの併用療法またはTKI単剤、中リスク群や高リスク群でTKI+ICIの併用療法またはICIの2剤併用療法を行うことが一般的です。
表1 薬物療法の種類、効果、副作用について
| 種類 | 作用機序 | 副作用 | |
|---|---|---|---|
| 分子標的薬 | 血管新生阻害薬 (TKI) |
腫瘍の血管新生を阻害して、腫瘍への血液(栄養)供給を抑制する。 | 高血圧、皮疹、手足症候群、下痢、嗄声、甲状腺機能障害、骨髄抑制、間質性肺炎など |
| 分子標的薬 | mTOR阻害薬 | がん細胞の増殖などに関わる情報伝達を阻害することで増殖を抑制する。 | 皮膚炎、口内炎、食欲不振、高血糖、高脂血など |
| 免疫治療 | 免疫チェック ポイント阻害薬 (ICI) |
がん細胞の表面にある免疫機能をブロックして、患者本人のリンパ球で癌細胞を攻撃できるようにする。 | 倦怠感、皮疹、下痢、悪心、内分泌機能障害(下垂体、副腎、甲状腺、糖尿病)、間質性肺炎、神経筋肉障害、肝・膵障害など |
表2 転移のある腎臓がんの予後予測分類(IMDC分類)
| 6つの予後予測因子 | あてはまる項目数 | ||
|---|---|---|---|
| 0項目 | 1から2項目 | 3項目以上 | |
| ① 初診時から治療開始の期間が1年以内 | 低リスク | 中リスク | 高リスク |
| ② Karnofskyの一般全身状態スコア(KPS)が80%未満 | |||
| ③ 貧血、ヘモグロビンが正常下限値未満 | |||
| ④ 補正Ca値増加、正常上限値を超える | |||
| ⑤ 好中球数増加、正常上限値を超える | |||
| ⑥ 血小板数増加、正常上限値を超える | |||